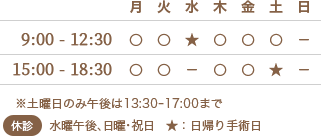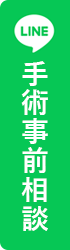耳鳴りは「明らかな体外音源がないにもかかわらず感じる異常な音感覚」と定義されています。
耳鳴りは「拍動性耳鳴」と「非拍動性耳鳴」に大別されます。
耳鳴りの分類
拍動性耳鳴
拍動性耳鳴の70%は体内に音源があり、原因として血管性耳鳴があります。
血管性耳鳴は耳周囲の血流異常により発生すると考えられ、動静脈奇形、動脈瘤、動脈硬化、血管性腫瘍、高位頸静脈球などがあります。
拍動性耳鳴の場合は、原因疾患の治療により耳鳴りの消失が期待できる場合があります。
非拍動性耳鳴
非拍動性耳鳴の大多数は慢性持続性耳鳴が占め、体内に音源はなく、他者には聞こえません。
これが多くの患者さんを悩ませている耳鳴りです。
聴こえが悪くなるとそれに伴い耳鳴りが生じてくることがよくあります。
慢性の耳鳴りの原因としては音を感じる機能に障害のある感音難聴が最も多いと考えられていますが、一般的に感音難聴は治療により回復することが難しい疾患が少なくないため、感音難聴に伴った耳鳴りが完全に消えないことも少なくありません。
治療
難聴の改善が期待できる時には、まず、その治療を行います。
難聴の回復が難しい場合には、耳鳴りが完全に消えないことも少なくありません。
そのような場合、耳鳴りの治療は、耳鳴りによる苦痛な状態や症状が軽くなること、気になる時間が少なくなることを目標に行われます。
以下に慢性の耳鳴りの治療を述べます。
薬物治療
耳鳴りの改善を期待してビタミン製剤、血流改善薬、血管拡張薬、ステロイド製剤などを、耳鳴りの苦痛を軽減する目的で抗けいれん薬、筋弛緩薬、局所麻酔薬、抗不安薬、抗うつ薬、漢方薬などを、耳鳴りに併せて起こる不眠に対して睡眠薬などを投与することがあります。
これらの治療の効果を示す証拠は少なく、副作用の問題もありますので、漫然と投与することは避けた方がよいと考えられます。
音響療法
人の脳には、音に対する感度を周囲の音のレベルに応じて変化させる機能があります。
このため、自分の周りの音が入ってこないと脳は活性化し、音を大きく聞き取ろうとする働きが生まれます。
この大きく聞こうとする脳の機能が過剰に働くと耳鳴りが起こると考えられています。
このため、聞こえが正常な人でも、音の全くない響かない部屋に数分いると耳鳴りが起こります。
難聴がある方は特に脳に届く音の量が少なくなるため、この大きく聞こうとする脳の機能が活性化しやすく、耳鳴りが起こりやすいと考えられています。
このように、脳に届く音の量が少ないことによって起こる脳の活性化が耳鳴りの原因の一つと考えられています。
したがって、脳に届く音の量を増やしてあげることが耳鳴りの治療になります。
音響療法は、脳に届く音の量を増やしてあげる治療法です。
音響療法には静寂を避ける方法、環境音楽を聴く方法、補聴器やサウンドジェネレーターを用いたTRT療法(Tinnitus Retraining Therapy)が含まれます。
音響療法の効果は、脳の過度な活性化に対する効果の他にも、マスキング効果(音にさえぎられて耳鳴りが聞こえなくなること)、耳鳴りへの順応、耳鳴りから注意をそらす効果、リラックス効果などがあります。
参考文献

- 「患者さん向け耳鳴診療Q&A」
一般社団法人日本聴覚医学会 金原出版株式会社