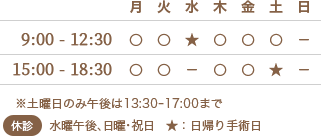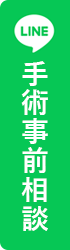嗅覚障害とは「においが判らなくなった」、「においの感じ方が今までと変わった」という状態です。
嗅覚障害になるとガス漏れを察知できなくなるなど日常生活で危険を伴います。
また、嗅覚は味覚とも関係が深く、食事が美味しくないなど生活の質も悪化します。
原因
におい成分は鼻から吸い込まれ嗅神経細胞に到達します。
嗅神経細胞はにおい信号を電気信号に変換し、嗅球に信号を伝えます。
その後、電気信号は嗅球、嗅索、大脳前頭葉に伝わり、においが認識されます。

(嗅覚障害診療ガイドラインより引用)
嗅覚障害は鼻腔から大脳までのあらゆる嗅覚路の異常によって生じえます。
異常が生じる部位により病態と原因が異なるため、以下の3つの病態に分類されています。
①気導性嗅覚障害
鼻呼吸時に吸入された空気が嗅神経細胞の存在する嗅裂部に到達できないために生じる嗅覚障害です。
主に、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎が原因となります。
②嗅神経性嗅覚障害
嗅神経細胞が傷害を受けて嗅覚の低下をきたす状態です。
感冒後嗅覚障害のように嗅神経細動へのウイルスの感染により嗅神経細胞が傷害を受ける場合と、顔面の外傷により嗅神経軸索が傷害を受ける場合があります。
③中枢性嗅覚障害
嗅球から嗅索、大脳前頭葉に至る頭蓋内の嗅覚路の障害により生じる嗅覚障害です。
原因は頭部外傷による脳挫傷が最も多いですが、脳腫瘍、脳出血、脳梗塞も原因となります。
またパーキンソン病やアルツハイマー型認知症などの神経変性疾患にも嗅覚障害が合併し、特にこれらの疾患の主症状発症前に嗅覚障害が出現することが知られています。
検査
問診
感冒、副鼻腔炎、外傷の有無、既往歴、内服薬などを問診で確認します。
気導性嗅覚障害以外は鼻内の形態に変化がありませんので、問診は重要です。
内視鏡
鼻内を観察し、ポリープなど気導性嗅覚障害の原因となる物理的障害の有無をみます。
基準嗅力検査/静脈性嗅覚検査
嗅覚の評価を行います。
CT/MRI
副鼻腔炎、脳腫瘍、脳梗塞などの鑑別に有用です。
治療
副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎が原因であれば、その治療を行います。
原因が明らかでない場合はステロイドホルモン剤の点鼻やビタミン剤、漢方薬の内服などを行いますが、改善が難しいこともあります。
嗅覚刺激療法
複数のにおいを毎日嗅ぐことにより嗅覚改善率が高くなると報告されています。