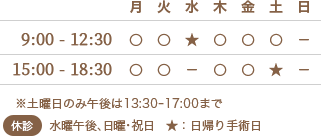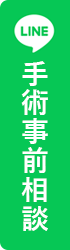滲出性中耳炎は中耳(鼓室)に液体がたまる病気です。
耳と鼻の奥をつなぐ耳管が正常に機能しなくなることで起こります。
耳管機能は10歳くらいまでは未熟で、50~60歳代以降で徐々に低下していきます。
そのため滲出性中耳炎はその2つの年齢層で多くみられます。
原因
耳管の働きが悪くなる病態として、アデノイドや口蓋扁桃が大きい場合、風邪・副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎などで鼻症状がひどい場合、加齢によって耳管の働きが衰える場合などが挙げられます。
耳管の働きが悪くなると、中耳の粘膜から分泌された液体が耳管を通ってのどに流れることができず、鼓室にたまってしまい、滲出性中耳炎になります。
鼻の奥(上咽頭)に発生した腫瘍が耳管を塞いで滲出性中耳炎を生じることもあり、長期に滲出性中耳炎が治らない場合には注意が必要です。
症状
鼓室内にたまった貯留液により、難聴、耳のつまった感じ(耳閉感)、自分の声が耳に響く(自声強調)、耳鳴りなどの症状が起こります。
滲出性中耳炎を放置すると癒着性中耳炎や真珠腫性中耳炎などの病気に移行する可能性があります。
検査・診断
- 鼓膜の観察(耳鏡、顕微鏡、内視鏡など)
鼓膜の観察で、鼓室内の貯留液を確認します。 - 聴力検査
- ティンパノメトリー
鼓膜に圧を加えて鼓膜の動きやすさを調べる検査です。滲出性中耳炎では鼓膜が鼓室の方向に凹むため、鼓膜に陰圧をかけた時の方が動きやすくなります。 - 内視鏡検査
上咽頭の腫瘍が原因で滲出性中耳炎になることがあるため、内視鏡で上咽頭に腫瘍がないか確認することがあります。
治療
鼻症状が滲出性中耳炎の原因となっていることが多いため、抗菌薬や消炎剤を内服して、耳や鼻の粘膜の働きを正常化し、滲出液がたまらないように治療します。
このような治療をしても改善しない場合には、鼓膜切開を行います。
鼓膜切開後の穴は通常数日で塞がることが多いです。
鼓膜切開をしても滲出性中耳炎を繰り返す場合は、鼓膜チューブを留置することで、滲出液の貯留を防止します。